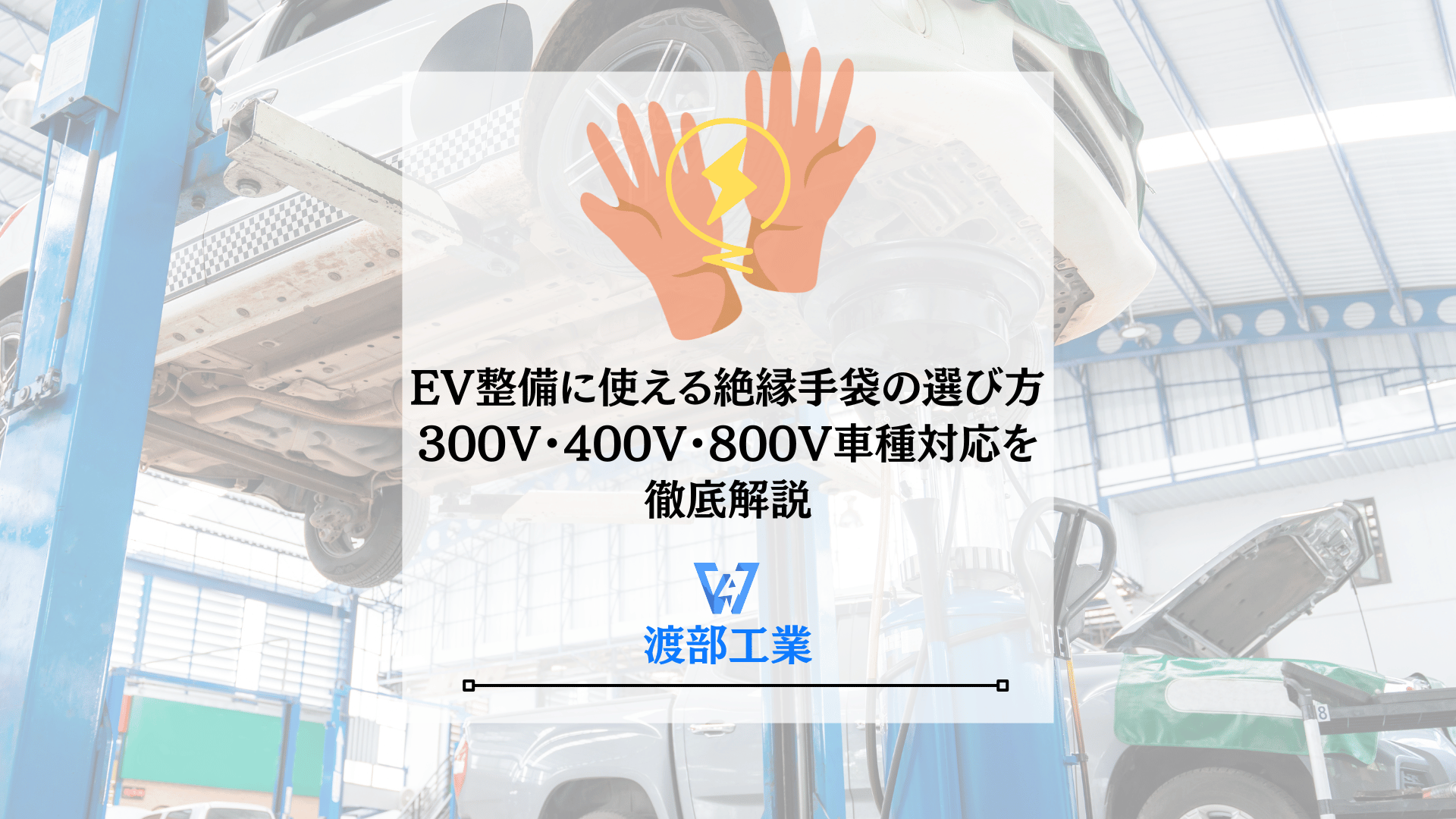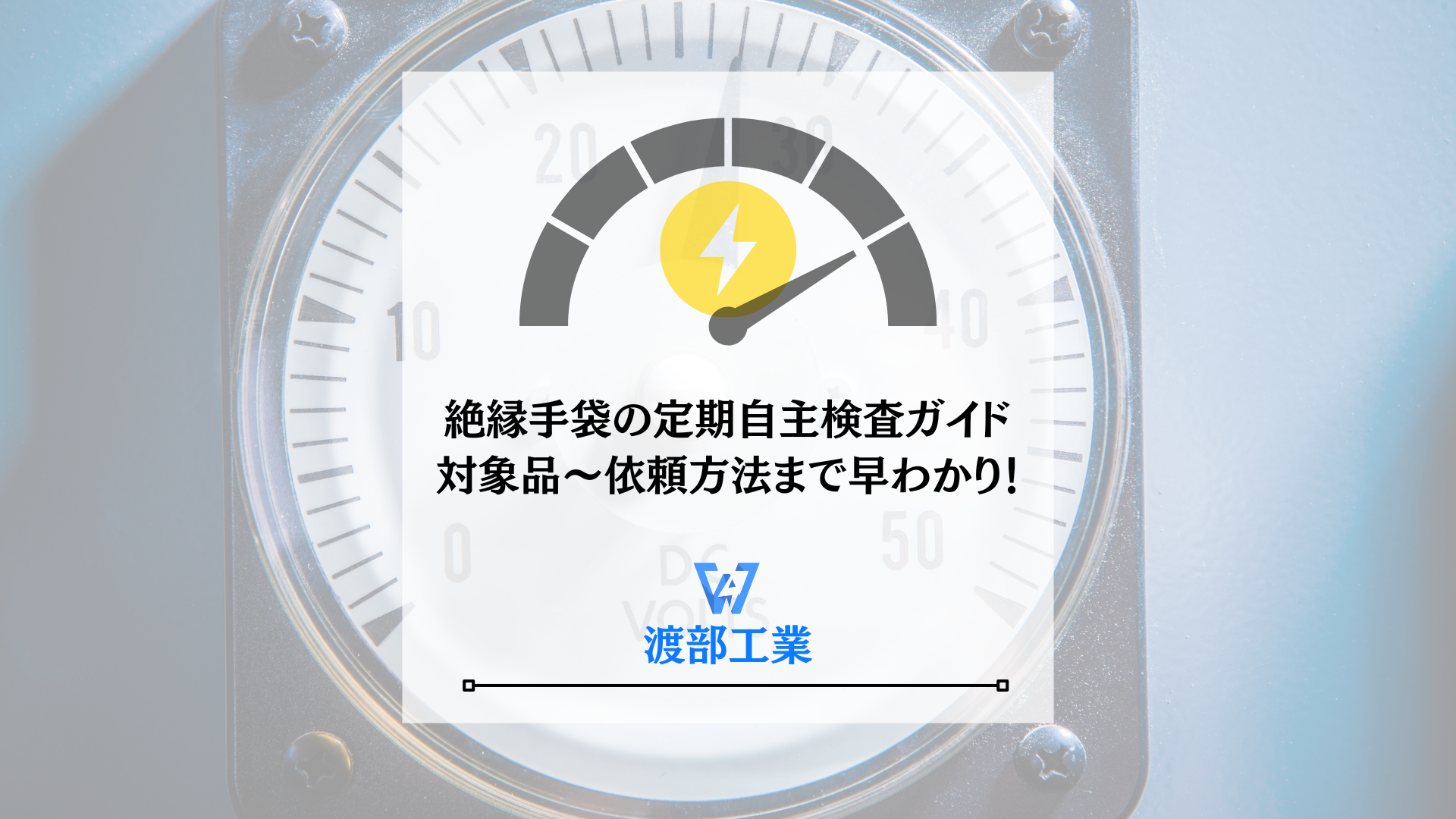中小の整備工場でもEVの取り扱いが進むなか、感電事故のリスクが高まっています。特に高電圧バッテリー車両の増加に伴い、絶縁手袋の正しい選定と運用が重要です。本記事では、電圧別に推奨される絶縁手袋とその特徴をわかりやすく解説します。
EV整備に絶縁手袋が必要な理由

EVの整備作業において、なぜ絶縁手袋の着用が欠かせないのか。その背景には感電リスクの存在や電圧上昇による危険性、さらに法令上の義務が関係しています。
感電リスクは「低圧車」でも存在する
「低圧」と呼ばれる比較的低い電圧のEVやハイブリッド車でも、電気作業では感電のリスクがあります。例えば、多くのハイブリッド車はおよそ200~300Vのバッテリーを搭載しており、この電圧は人体にとって十分危険なレベルです。一般に50Vを超える電圧は感電の恐れがあるとされ、200V以上ならなおさら深刻な事故につながりかねません。したがって、低圧の車両であっても絶縁手袋を着用し、感電防止策を徹底する必要があります。
バッテリー電圧の上昇で作業リスクも増加
近年のEVではバッテリー電圧が400Vや800Vとますます高電圧化しています。電圧が高くなるほど電流も大きく、接触や短絡時に放出されるエネルギーが増すため、作業中のリスクも格段に上昇します。高電圧ではわずかな隙間でもアーク放電(火花放電)が発生しやすくなり、絶縁不良や工具の接触による事故の危険性が高まります。つまり、バッテリー電圧の上昇に伴い、作業者はより高度な安全対策が必要になるのです。
絶縁手袋は法令で定められた保護具
絶縁手袋は単なる任意の安全対策ではなく、法令によって使用が義務付けられた保護具です。日本の労働安全衛生規則では、高圧および低圧の活線作業に従事する際、作業者は絶縁用保護具(電気用ゴム手袋など)を着用しなければならないと定められています。EVの高電圧システムの整備作業はこの規則の適用範囲に含まれ、安全面だけでなくコンプライアンス(法令遵守)の上でも絶縁手袋の着用は欠かせません。
EV整備で求められる「作業性と安全性」の両立
絶縁手袋は安全確保に必須ですが、それによって作業がしにくくなるのは避けたいところです。EV整備ではいかに安全性を保ちながら作業性も確保するかがポイントになります。
M5のネジを手締めできるかが作業性の指標
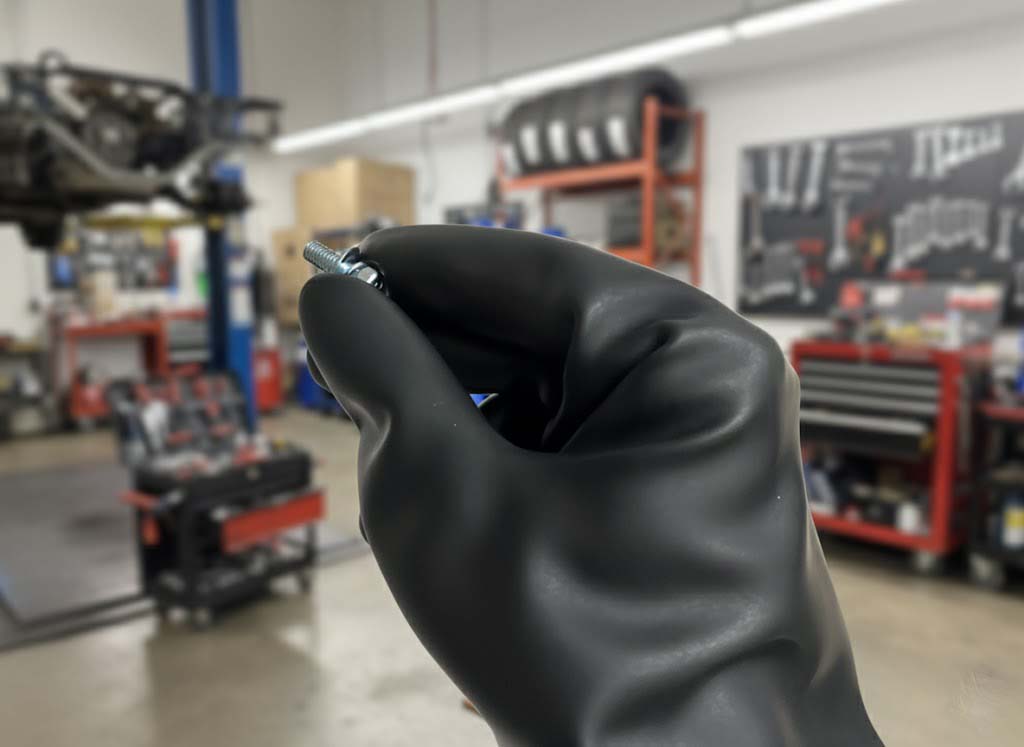
EV整備では、高い安全性を確保しつつ細かな作業を正確に行う必要があります。絶縁手袋を着けた状態でも細かいボルトやナットを扱えるかどうかが重要で、その一つの目安が「M5ネジを手で締められるか」です。絶縁手袋を装着したままM5程度の小さなネジを指先で回せるほどの作業性が発揮できれば、手袋を外さずに多くの配線接続や部品交換作業を安全に進められます。反対に、分厚すぎる手袋では細かな部品をつかみにくくなり、いくら安全でも作業効率が落ちてしまいます。絶縁手袋選びでは、このような作業性も考慮して選定することが大切です。
薄手でも確実な絶縁性能を確保する505型の特長

渡部工業の「505型」絶縁手袋は、薄手でありながら高い絶縁性能を持つことが大きな特長です。従来の低圧用手袋(例えば507型)の約半分の厚み(約0.5mm)に抑えつつ、JIS T8112規格(クラス J00)に適合し直流750Vまでの耐電圧性能を確保しています。薄手ゆえ指先の感覚が伝わりやすく、狭い箇所での配線作業やコネクタの脱着も手袋をしたままスムーズに行えます。また、手袋内側に特殊な加工(サンドブラスト)が施されており、ゴム手袋特有のベタつきが少なく、長時間の作業でも手に張り付きにくい設計です。これにより安全性と快適さを両立し、多くの整備士から支持を得ています。
EV整備で扱う電圧の種類と危険性(AC/DCの違いを理解)
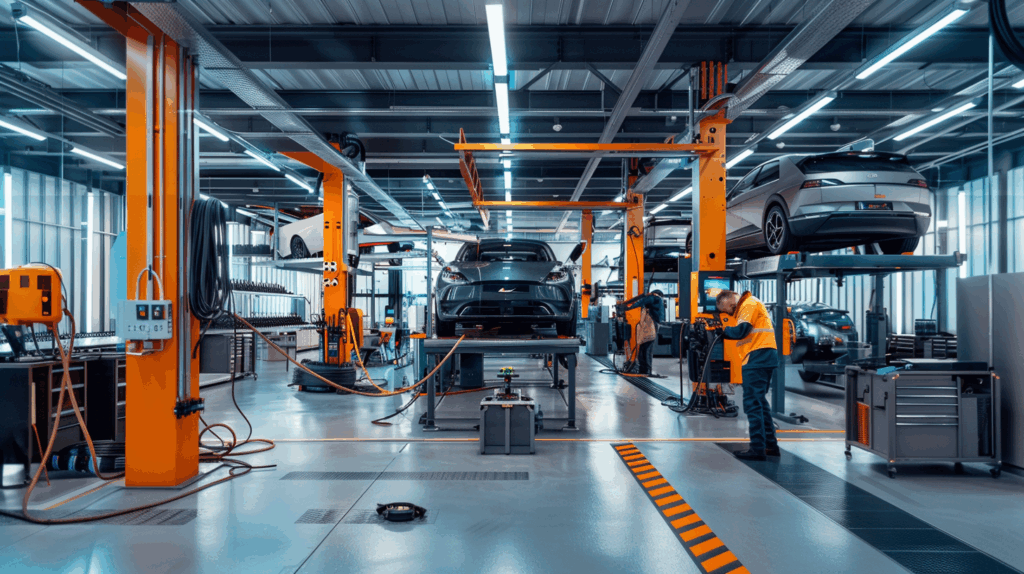
EVには複数の電圧系統が存在し、それぞれに応じた危険性があります。また直流(DC)と交流(AC)では電気の振る舞いが異なるため、整備時の注意点も変わってきます。
補機系はDC300V以下、駆動系はDC400~800V
EVでは車載する電源系統に複数の電圧レベルが存在します。エアコンやDC-DCコンバータといった補機系統では概ね直流300V以下の電圧が使われる一方、モーターを駆動する主バッテリー系統は車種によって直流400V級から最大800V近くに達します。従来のハイブリッド車では200~300V程度が主流でしたが、近年の電気自動車では高出力化のため400V以上が一般的となり、最先端では800Vシステムも登場しています。整備者は、自分が作業する回路がどの電圧帯に属するかを把握し、それに適した絶縁手袋を選ぶ必要があります。
インバータ出力部はAC600V前後になる
EVの駆動モーターは、直流バッテリーの電力をインバータで交流電力に変換して動かしています。そのインバータ出力部では、バッテリー電圧が高い車種ほど交流の出力電圧も高くなります。例えば400V級のEVではモーターへの三相交流が概ねAC300V台(線間電圧の実効値)ですが、800V級のシステムではAC600V前後にも達します。こうした低圧~中圧の交流回路にも作業者が触れる可能性があるのであれば、直流だけでなく交流に対する絶縁性能も備えた保護具が必要です。
直流と交流では「放電挙動」や「耐電圧条件」が異なる
EV整備では直流(バッテリー)と交流(モーター駆動)の両方を扱いますが、これらは電気の挙動が異なるためリスクの性質も変わります。直流は一度アーク(火花)が発生すると持続しやすく、なかなか消えないため大事故につながりやすいという特徴があります。交流は周期的に電圧が0になる瞬間があるのでアークが消えやすい一方、数値は実効値で表記されるため実際のピーク電圧は約1.4倍に達します。絶縁手袋の仕様には「使用可能電圧:AC○○V/DC○○V」のように両方の上限値が示されており、例えばある手袋では交流300V・直流750Vまで使用可能です。このように、直流と交流で放電や絶縁の条件が異なる点を理解しておくことが重要です。
電圧別に見る絶縁手袋の選び方
扱う電圧に合わせて、使用すべき絶縁手袋の種類も変わります。ここでは想定される電圧帯ごとに、適切な手袋モデルの選び方を解説します。
DC300V以下には507型・505型(低圧用)
直流300V以下の補機系統など低電圧の回路であれば、低圧用の絶縁手袋で対応可能です。具体的には渡部工業の507型や505型が該当し、いずれもJIS T8112クラス J00に適合した手袋です。厚み約1.1mmの標準タイプ507型は交流300V/直流750V以下に使用でき、内部配線やコンデンサ点検などに適しています。より薄手の505型は作業性が高く、小さなボルトの着脱や狭所での作業に向いていますが、同じく直流750Vまでの絶縁性能を備えており安全性も万全です。300V以下の作業では、こうした低圧カテゴリの手袋を使うことで安全性と効率を両立できます。
DC400~800VやAC600V前後には508・520型(低圧~中圧用)
EVの駆動系やインバータ周辺では、直流400~800V級や交流600V前後の電圧を扱います。この領域では508と520を使い分けるのが現実的です。508は「AC600V以下用」として設計されたモデルで、交流側の工程(例:インバータ二次側がAC600V以下に収まる作業)に適した選択肢です。
一方で、作業電圧が交流600Vや直流750Vを超える可能性がある場合は520を推奨します。520は中圧向けの高い耐電圧を備え、AC/DCどちらでも余裕を持って対応できます。現場では、実際の電路(AC/DC・最大電圧)を必ず確認し、AC600V/DC750V以下なら508、AC600V近傍/DC750V近傍なら520という基準で選ぶと迷いません。なお、両製品とも定期自主検査(耐電圧試験)の対象となるので、ご注意ください。
【比較表】電圧帯ごとの適合手袋早見表
| 電圧帯 | 種別 | 想定用途 | 渡部工業モデル | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| DC300V以下 | 低圧 | 補機・内部配線 | 505・507 | JIS T8112 J00適合。J00ながらDC750Vまで対応する設計で安全余裕を確保 |
| AC600V以下 | 低圧 | インバータ二次側がAC600V以下の工程 | 508 | AC600V以下用。交流工程での実用解。交流300V超で使用する場合は定期自主検査が必要 |
| AC600V超/DC750V超 | 中圧 | 駆動バッテリー・主ハーネス/インバータ出力 | 520 | 安全マージン重視ならこちら。AC/DCとも余裕のある耐電圧。定期自主検査が必要 |
※実際の作業電圧を必ず確認したうえで、製品を選定してください。
【まとめ】EV整備では電圧帯に応じた手袋選定が安全のカギ
EVの整備現場では、補機・内部配線のようなDC300V以下の低圧領域から、駆動バッテリーやインバータ出力部のDC400~800V級まで、幅広い電圧を扱います。作業する電圧帯に応じて、505・507・508・520といったモデルを正しく使い分けることが、安全確保の第一歩です。
特に600V前後の領域では、区分上は低圧でも感電エネルギーが高く、必要に応じて520など安全マージンを確保できる手袋を使用しましょう。逆に、補機系や内装電装などDC300V以下の工程では、作業性を重視して507や505を選ぶと効率的です。
EVは年々高電圧化が進み、今後は400V・800V級の車両が主流になります。現場では「自分の扱う電圧を把握し、JIS T8112適合の絶縁手袋を選ぶ」ことを基本とし、用途に応じた保護具を常に最適化する姿勢が求められます。